事業価値算定に関わるポイント 5-2 DCF法 リスクフリーレート・負債コスト
- Shuichi Kobayashi

- 2022年1月2日
- 読了時間: 5分
更新日:2024年7月7日
更新:2024年7月7日

円安進行にあわせ、「金利」が上昇してきました。WACCで使用する金利について最近の金利などを参照して更新します。さて、すこし改めて“前置き”です。事業価値/株式価値は、M&A当事者、資金調達当事者、各位が共有できる「フォーミュラ」で計算されます。
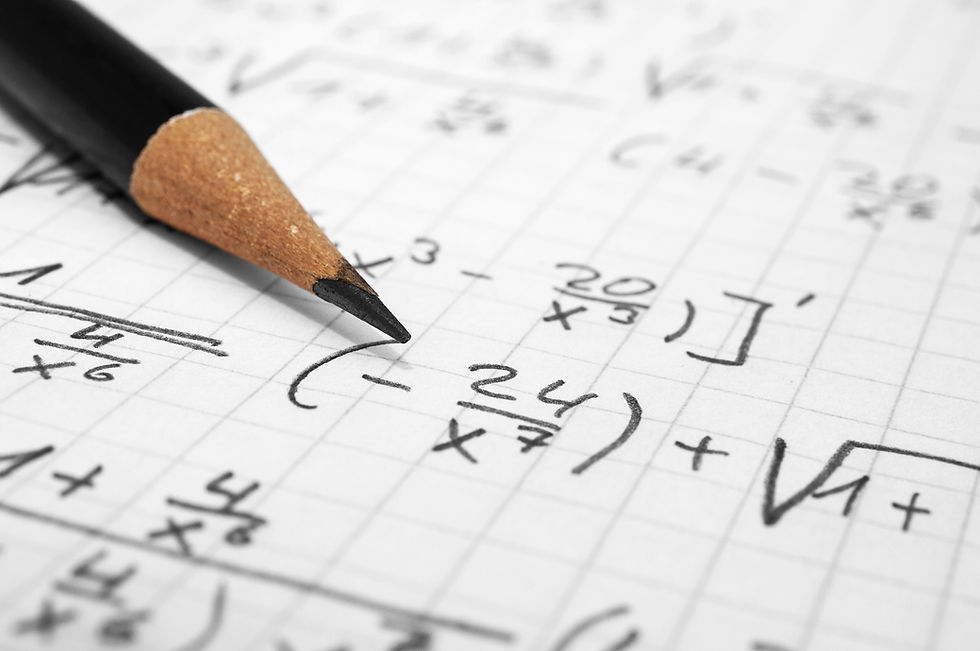
当事者が合意できればどんなフォーミュラでも構わないはずです。

たとえば、交渉として直近増資額、純資産、EBITDA倍率、DCF法、どれを参照して株価(時価)を決定して良いわけです。
他方、スタートアップのフェーズが上場準備に近づくほど、あるいはM&Aの案件規模が大きいほど、当事者(の数)は潜在、顕在ともに増えます。

そうなるに従い、共有できるフォーミュラは「適切な算定手法・使用されるインプットの適切性」「客観性」「正確性」が担保されるものが求められることになります。

WACCは、DCF法のフォーミュラで採用される最も重要な構成要素のひとつです。

そして今回はWACC論点の掘下げ、リスクフリーレートの解説を若干更新します。
ちなみに、シリーズ「事業価値算定のポイント」は、以下の章立てです。
1.企業価値評価における事業価値、株式価値 <クリック
2.類似企業比較法について <クリック
3.DCF法 と 継続価値(ターミナルバリュー) <クリック
4.支配権プレミアム&流動性ディスカウント
4-1 支配権プレミアム <クリック
4-2 非流動性ディスカウント <クリック
5-1DCF法と割引率(WACC)について <クリック
5-2WACC計算 リスクフリーレート・負債コスト (本日更新)
5-3WACC計算 サイズリスクプレミアム
5-4DCF法 期央主義
6.ベンチャー企業のバリュエーションにおける割引率
リスクフリーレートは、国債利回りを使用することが一般的です。

では、リスクフリーレートは何年の利回りを採用するか?
何年物の国債利回りを参照するか、に際し、基本的なコンセプトとしては、DCF法―継続期間で触れましたが、無限の期間のキャッシュフローの割引計算をするため、「長ければ長いほうが良い」ということになります。他方で、あまりに長いと市場での流通量等の問題等から、実態を反映していないと考えられることもあるので40年国債などは、実際使われていないと思います。これまで見たことはありません。
実務上は日本においては、10年債を採用することが多いように思います。とうとう、1%になりました。
国債金利情報 | (単位 : %) | |||
基準日 | 10年 | 20年 | 30年 | 40年 |
R6.6.11 | 1.035 | 1.81 | 2.111 | 2.311 |
R6.6.12 | 1 | 1.784 | 2.084 | 2.283 |
R6.6.13 | 0.982 | 1.762 | 2.063 | 2.247 |
R6.6.14 | 0.95 | 1.732 | 2.044 | 2.227 |
R6.6.17 | 0.947 | 1.755 | 2.068 | 2.271 |
R6.6.18 | 0.963 | 1.777 | 2.089 | 2.292 |
R6.6.19 | 0.955 | 1.758 | 2.071 | 2.271 |
R6.6.20 | 0.973 | 1.769 | 2.068 | 2.259 |
R6.6.21 | 0.999 | 1.792 | 2.086 | 2.275 |
R6.6.24 | 1.01 | 1.811 | 2.108 | 2.3 |
R6.6.25 | 1.02 | 1.824 | 2.121 | 2.312 |
R6.6.26 | 1.044 | 1.851 | 2.155 | 2.352 |
R6.6.27 | 1.092 | 1.881 | 2.188 | 2.383 |
R6.6.28 | 1.062 | 1.848 | 2.153 | 2.349 |
何年債の国債利回りを採用するかは、CAPMの計算上、エクイティリスクプレミアムの計算方法とセットで考える必要がありますが、前回紹介した一般に最も利用されるIbbotson Assosiates Japanのエクイティリスクプレミアムが日本は10年、米国は20年の年限の国債利回りを採用していることも、10年国債が実務慣行の一因だと思います。
参考までに更新履歴ベースですが、過去の10年国債利回りは以下です。
2022年12月末日 0.454%
2023年 7月末日 0.605%
いまとなっては「古い話」になりましたが、WACC計算におけるリスクフリーレートがマイナス値を示していた場合は?(数年前(H31~R2)悩ましい問題でした。)
ゼロ%とすべきか、それともマイナス値をそのまま採用すべきか。
・市場で観測されているデータを基準日、あるいは基準日までの一定期間の平均などでそのまま採用すべきという考え方
・ゼロとすべきという考え方
いずれもあると思いますが、前者がポリシーとしては客観性が良いように思います。
WACC計算における負債コストの論点
次に負債コストの解説をします。
負債コストとしては流通している社債の利回りを参照することが一般的と思われます。ただし、対象会社の負債コストを使用するケースも散見されます。

ただ、リスクフリーレートに比べると論点が多く、悩ましい個所のように思います。
WACC計算における負債コストの格付けとしてどれを採用すべきか?
負債の格付けは、国内においては、AAA~B、アメリカにおいては、Aaa, Baaの種類があり、どれを採用すべきかという点が論点になります。

これについては、評価対象会社が格付けを採用していればその格付けを参考にすべきですが、取得していないケースの方が多いように思います。
どうするかですが、はっきり言って正解がないので、あくまで一例として以下記載します。
優良な会社:国内はAAないしA、米国であれば、Aaa, Baaの平均を採用するなど
普通な会社:国内はBBBやBB、米国であればBaaを採用するなど
芳しくない会社:普通な会社に対して数パーセントの上のせを行うなど
こう考えると、わたしは通常BBBが適当だとおもいます。わたしは、BBBを利用します。ちなみに、日本証券協会HP:格付投資情報センターから採取した2023年7月31日以降、最近まで、BBB10年債の利回りは、・・・10年がない。。 8年もので1.6%です。
あとは、評価対象会社の実際の負債コストを採用することもあるのですが、負債コストとして採用するには以下の要素を考慮する必要があります。
無担保の借入利率であるべき
キャッシュフローの期間に可能な限り近い、長期間の負債コストであるべき
リースの割引率には調達コスト以外の要素も入っているため妥当ではない
そう考えると、何を採用すべきかわからないところになってきますが、評価対象会社の実際の負債コストを勘案しつつマーケットデータの要素も加味するということでよいかと思います。
負債コストに限らないですが、割引率は必ずしも一意に決まるものではなく、評価人によって、ある程度の差異は発生せざるを得ない項目です。
WACC計算における負債コストは何年の利回りを採用するか?
これもリスクフリーレートと同じで基本的なコンセプトとしては、無限の期間のキャッシュフローの割引計算をするため、「長ければ長いほうが良い」ということになります。
他方で、あまりに長い社債利回りは流通量も少なく、実態を反映していなかったり、個別の事情で数字がぶれている可能性があったりするので悩ましいところです。10年債で良いかと思う事が多いです。最近、10年債がBbbではない。ですが。







コメント